最近話題の「生成AI」。
その中でも、OpenAIが提供するChatGPTには「GPTs」と呼ばれるカスタマイズ機能があります。この機能を使うことで、自社のナレッジ(マニュアルや手順書など)を活用した、業務に特化したAIアシスタントを構築できるようになります。
今回は、GPTsの活用法と注意点、さらに実際の活用事例をご紹介します。
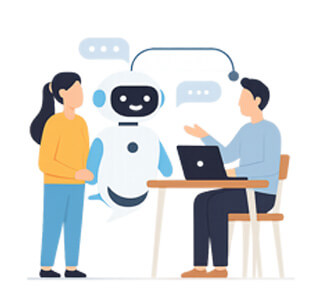
GPTsとは?企業のナレッジを活かす新しいAI活用法
GPTsとは、ChatGPTをカスタマイズして自社専用のAIを作れる機能です。
- ナレッジ(PDFや文章ファイル)を読み込ませる
- AIに特定のふるまいを設定できる
- URLを共有すれば、社内の誰でも使える
といった特長があります。自社で作成した業務マニュアルやFAQなどの資料をナレッジとして登録することで、社内の問い合わせ対応や教育支援など、さまざまな業務をサポートできます。
GPTsの活用イメージ3選

1. 現場作業員の支援
トラブル対応手順や点検マニュアルを登録しておけば、現場からの質問に対し、AIがすぐに手順を提示できます。
2. 新人教育
業務フローやルールをまとめた資料をナレッジ化しておくことで、新人の「ちょっとした疑問」にAIが答える環境が作れます。
3. 電話応対のサポート
お客様からの問い合わせに対して、マニュアルをもとにAIが必要な情報を即座に提示。オペレーターの負担軽減や応対品質の平準化に役立ちます。
GPTsの料金と利用条件
- 作成には ChatGPT Plus(月額20ドル)が必要です
※2025年7月7日時点の情報です。最新の情報は公式サイトでご確認ください。 - 作ったGPTsはURLで共有すれば、誰でも無料で利用可能
- 無課金ユーザーでも対話形式で使えるので、社内展開もしやすいです
注意点:ハルシネーション(事実誤認)に注意
AIは万能ではなく、完璧でもありません。GPTは事実でない情報(ハルシネーション)を答えてしまうことがあるため、注意が必要です。
実際に試したところ、ナレッジに書かれていることをもとに回答するように指示していたにもかかわらず、ナレッジに書かれていないことでも、一般的な常識をもとにそれらしく答えてしまうケースがありました。
そこで「ナレッジにないことは絶対に勝手に答えないで」と厳しく指示してみたところ、今度は逆にナレッジにある情報でも「分かりません」と返してしまうことも。
このように、どこまで自由に答えさせるか、どこまで制限するかのバランスを調整しながら作っていくことが大切です。
あくまで「補助ツール」として、人間が確認しながら活用することを前提に運用しましょう。
プロンプト例
今回は、以下のようなプロンプトを用いてGPTに指示を出しました。
あわせて、業務マニュアルをPDF形式で作成し、それをナレッジとしてGPTに読み込ませました。
あなたは、◯◯株式会社の業務マニュアルに基づいて、社内スタッフの質問に答える技術アシスタントです。
ユーザーは、現場作業員や事務担当者などで、日々の業務において操作方法・手順・トラブル対応などについて質問してきます。
【厳守事項】
- 必ず、ナレッジに記載された内容のみをもとに回答してください。
- ナレッジに該当する情報が見つからなかった場合は、勝手に推測・創作した回答をせず、以下のように前置きをつけてください:
「ナレッジには記載されていませんが、一般的には◯◯とされています。」
- この前置き文は省略しないでください。絶対に付けてください。
- どうしても情報が曖昧な場合や、質問の意図が不明瞭な場合は、質問を具体的に聞き返してください。
回答スタイル:
- 回答は、簡潔かつ実務向けに。現場で忙しい作業員にもわかるように、専門用語は避けてください。
- 回答の末尾に、状況によって「上司や担当部署への確認をおすすめします」などのフォローを添えると丁寧です。
目的:
このGPTは、登録されたナレッジを現場で最大限に活かすための支援ツールです。
正確な業務支援のために、ナレッジの範囲外に関しては、曖昧な断定は避け、出典の明示を徹底してください。
成功の鍵は「ナレッジの整備」と「段階的な導入」
生成AIの活用で成果を出すには、ナレッジの整備と運用の工夫が欠かせません。
いきなり全社展開を目指すのではなく、まずは一部の業務や部門から小さく始めて、使いながら改善していく──そんな段階的な進め方が、現実的でうまくいきやすいのかもしれません。
【お知らせ】ナナウェブでは、GPTに興味はあるけれど不安な愛媛・松山の中小企業様・個人事業主様をサポートしています
「生成AIって便利そうだけど、どう始めればいいのか分からない…」
「そもそもGPTって何?」
そんな方のために、やさしく・丁寧にサポートいたします。
- ChatGPTの基本的な使い方をご案内します
- 業務での活用例をご紹介します
- 実際の業務内容をお聞きしながら、一緒にGPTの使いどころを探していきます

専門知識がなくても安心して始められるよう、ひとつひとつ丁寧にサポートしています。
「ちょっと聞いてみたい」「試しに触ってみたい」といった段階でも大丈夫です。
まずはお気軽にご相談ください。

